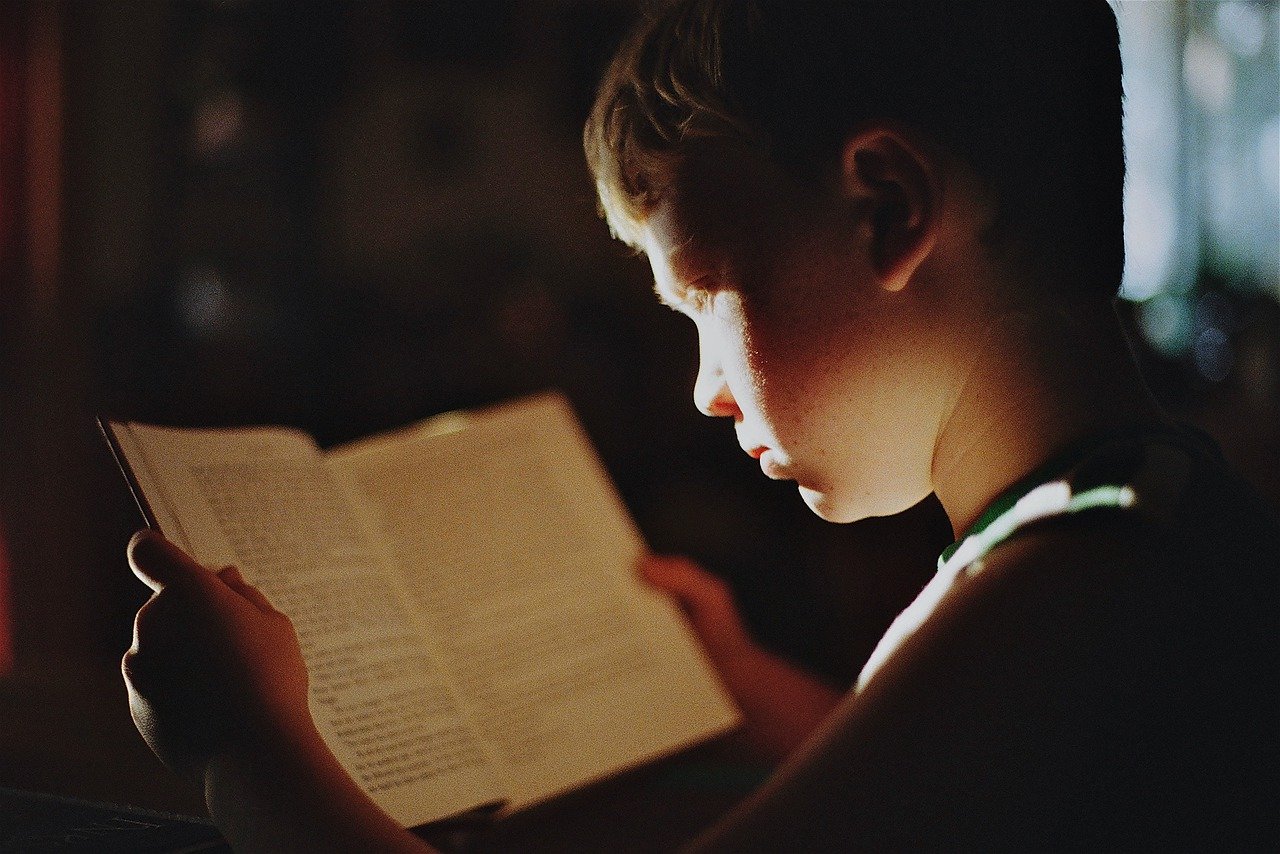メアリー・バフェット著、デビッド・クラーク著。著者のメアリー・バフェットはウォーレン・バフェットの息子の元夫人です。
以下、個人的な備忘録。
1950年代から1973年まで
バフェットはコロンビア大学でベンジャミン・グレアムの授業を受け、その後は彼の下で働き、大きな影響を受けています。
バフェットが師匠グレアムから学んだことは2つあり、1つは師匠グレアムが1929年からの大暴落(▲88%)に逃げ遅れて瀕死の重傷を負ったこと。もう1つは業界の二番手/三番手クラスの銘柄(最後の一服ぐらいは出来るという意味で「シケモク」株)を購入対象にしたことです。
1960代後半に株価は大きく上昇し始め、1973年にバブルの頂点に達し、その後▲45%の暴落を記録しています。
バフェットは1950年代から師匠に倣って安値で放置されていた二番手/三番手クラスの銘柄を購入し、1969年には高値で全てを売却しました。つまり、師匠の戦略を見習いつつ、しかし師匠の1930年代とは同じ轍を踏まないように早めに撤退をして事なきを得ています。
株式を売却後は、現金を握り締めたまま何もすることはありませんでした。バフェットにとって人生で最も長い3年間でした。
1973年末
第一次オイルショックによって株価が暴落した後、バフェットは狂ったように株を買い始めます。
しかし、この時期に主に購入した株は以前のような二番手/三番手クラスの銘柄ではなく、「永続的な競争優位性を持つ企業」の株でした。
二番手/三番手クラスのシケモク株は暴落前に売り抜けるという運命(さだめ)にありますが、「永続的な競争優位性を持つ企業」は安心して保有し続けられるという決定的な違いがあります。
2008年
前年のサブプライムローン問題を発端とした株価急落に伴なって、バフェットは有利な条件でアメリカ有数の大企業の株を大量に買っていきます。
永続的な競争優位性を持つ企業
バフェットの考え方はシンプルです。
世の中には2種類の株しかありません。ほんの僅かな超優良企業とそうでない企業です。
超優良企業とは、長い歴史を有し、文化の中に根ざし、安定的であり、従って将来の収益を高い確率で予測することができます。それは同時に、その企業の本質的価値を高い確率で計算できるということでもあります。
ここまで来れば、バーゲンハンターの残りの仕事は「対象企業の株価が暴落するのを待つ」という誰にでもできる簡単なお仕事になります。
逆にバフェットが買わない銘柄には以下の特徴があります。
- 価格競争に巻き込まれる企業。ブランド力がなく差別化が困難。例えば航空会社、自動車、CPU製造。
- 常に改善や改良を求められる業界。IT企業が典型。
本書における企業の分析方法
バフェットは自己の分析手法を公式していないと思いますが、本書では下記の2点を使って簡易的な分析をおこなっています。
- 長期間のEPS(1株当たり純利益)を見る。安定かつ右肩上がり。
- 長期間のBPS(1株当たり純資産)を見る。一貫して増加傾向。
もちろん、上記は必要条件でしかなく、事業そのものに「永続的な競争優位性」が十分条件になります。
本書における分析対象
本書では、バフェットの株式ポートフォリオのうち下記17銘柄について競争優位性を含めた分析をおこなっています。
いずれもバフェットの投資手法が確立した後の銘柄になります。
- アメリカン・エキスプレス・カンパニー
- バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(BNYメロン)
- コカ・コーラ・カンパニー
- コノコフィリップス
- コストコ・ホールセール・コーポレーション
- グラクソ・スミスクライン
- ジョンソン・エンド・ジョンソン
- クラフトフーズ
- ムーディーズ・コーポレーション
- プロクター&ギャンブル・カンパニー
- サノフィ
- トーチマーク・コーポレーション
- ユニオン・パシフィック・コーポレーション
- USバンコープ
- ウォルマート
- ワシントン・ポスト
- ウェルズ・ファーゴ&カンパニー
感想
ウォーレン・バフェットの投資方法を概観できる入門書。所要時間2時間。
(了)